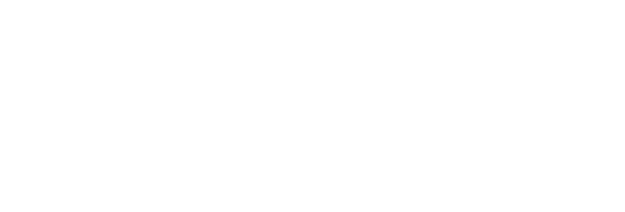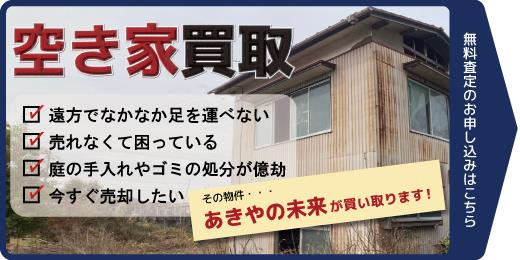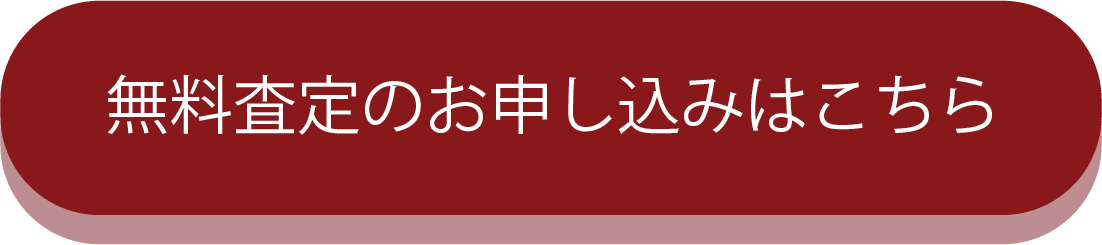リースバックにおける定期借家契約の仕組みとは?
リースバックを初めて検討している方にとって、「定期借家契約」という言葉はあまり聞きなれないかもしれません。
リースバックにおける賃貸借契約は、「定期借家契約」と「普通借家契約」の2種類がありますが、リースバックの多くは定期借家契約です。
定期借家契約は、契約期間が2~3年とあらかじめ設定されており、満了時には退去するのが一般的な流れです。これは、定期借家契約が更新を前提としない契約方式であることに由来します。ただし、貸主・借主双方が合意すれば、再契約によって住み続けることも可能です。
定期借家契約の性質や更新の有無についてよく理解し、注意点を確認しておくことで、リースバックをより安心して活用できます。
リースバックの賃貸借契約「定期借家」と「普通借家」はどう違うの?
リースバックの「定期借家契約」と「普通借家契約」には、どのような違いがあるのでしょうか。
ここでは、それぞれの仕組みと特徴を解説します。
【定期借家契約】
- 契約期間は一般的に2~3年程度で、期間満了とともに契約も終了となる。
- 再契約を希望する場合は、貸主であるリースバック業者の合意が必要である。
- 家賃は普通借家契約と比べて安く抑えられることが多い。
- 短期間の居住を予定している方や、家賃負担を軽減したい方に向いている。
【普通借家契約】
- 契約更新が前提であり、借主の居住権が強く保護される。
- 家賃は高めに設定されやすい(リースバック業者にとっては退去の見通しが建たず、資金回収や物件再販売など資産運用上のリスクがあるため)。
- 長く住み続けたい方に向いている。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、ライフプランに合わせて選ぶことが大切です。
リースバックにおける賃貸借契約については、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
普通借家契約・定期借家契約の違いや契約前に知るべき注意点
定期借家契約の満了後はどうなる?再契約の仕組みを解説
前述のとおり、リースバックにおいて定期借家契約を締結した場合、契約期間の満了とともに賃貸契約は終了し、物件から退去しなければならなくなります。定期借家契約は法律上、自動更新が認められておらず、期間延長はできません。
しかし、貸主であるリースバック業者と借主の双方が合意すれば、「再契約」という形で住み続けることができます。再契約を希望する場合は、契約の終了が近づいてから交渉するのではなく、早い段階で意思を伝え、条件について確認しておくことが重要です。
また、業者との信頼関係が築けていれば、再契約に前向きな対応をしてくれる業者も少なくありません。リースバック契約前に定期借家契約の性質を十分に理解し、長期的な住まいの計画を立てておくことで、安心してリースバックを活用できるでしょう。
なぜリースバックで定期借家契約が使われるのか?
リースバックの多くで定期借家契約が採用されていますが、それはなぜでしょうか。

定期借家契約は、一定期間で契約を終了できるため、リースバック事業者にとってリスク管理しやすい点が大きな理由です。特に、再販売の予定や収益計画のある物件では、契約更新が義務付けられない定期借家契約が適しています。
一方で、借主側にも「何年住めるか」が明確になるという安心感があります。リースバックで定期借家契約が広く採用されている背景には、貸主・借主双方にとって合理的な契約形態であるという実情があるのです。
次に、定期借家契約のメリットとデメリットを具体的に見ていきましょう。
リースバックで定期借家契約を選ぶメリット
定期借家契約は、貸主(リースバック業者)と借主双方にとって、次のようなメリットがあります。

【貸主】
- 契約期間の終了とともに自動的に契約が終了するため、物件の将来活用計画を柔軟に立てやすい。
- 長期にわたる入居者の居住権に縛られず、売却後の経営判断がしやすい。
【借主】
- 住める期間が明確に決まっていることで、計画的に住み替え準備ができる。
- 普通借家契約に比べて、家賃が割安になる傾向がある。
リースバックで定期借家契約を選ぶことは、貸主と借主の立場を明確にし、双方のリスクをコントロールできる合理的な選択肢と言えるでしょう。
リースバックにおける定期借家契約のデメリットと対策
リースバックで利用される定期借家契約は、メリットだけでなく、デメリットもしっかり確認しておく必要があります。
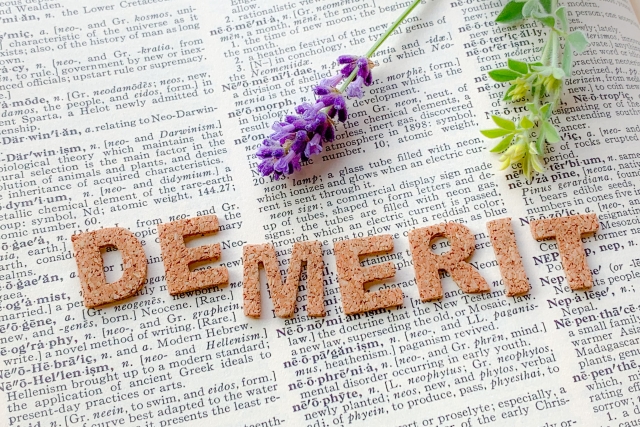
定期借家契約の最大の注意点は、契約期間満了時に自動更新がなく、原則として退去が求められる点です。特に、長期的に同じ住まいで暮らしたいと考える方にとっては、大きな不安要素となります。
また、定期借家契約では、途中解約が制限されやすく、やむを得ない事情があっても退去のタイミングに制約が生じることがあります。さらに、再契約時には家賃の値上げが行われる可能性も否定できません。
これらのリスクに備えるには、再契約の可否や条件を事前に確認し、契約内容を十分に理解することが重要です。契約条項は必ず書面で明示されるため、納得できるまで説明を受けましょう。あらかじめ内容を把握しておけば、定期借家契約でも安心して長期的に活用できます。
古い家はリースバックできるのか?
築年数の古い物件でも、条件を満たせばリースバックを利用することは可能です。
ポイントとなるのは、建物の構造や状態、そして立地条件です。木造住宅でも、定期的な修繕が施されており、瑕疵がなければリースバックの対象となるでしょう。
ただし、定期借家契約の締結にあたって、築年数が大きく影響するケースもあります。例えば、審査では建物の耐久性や安全性が重視されるため、築古物件でそれらが不明確な場合、契約が難航することがあります。
また、立地が過疎地で賃貸需要が極端に低い場合も、リースバックが成立しづらくなる要因です。築年数だけで判断せず、建物の現状や地域特性を踏まえて相談することが大切です。
まずは、定期借家契約を前提としたリースバックが可能かどうか、業者に具体的な審査を依頼してみましょう。
リースバックの利用が難しいケースを詳しく解説!
リースバックは、自宅に住み続けながら資金を得られる便利な仕組みですが、すべての物件で利用できるわけではありません。また、定期借家契約を前提としたリースバックでは、契約条件や審査基準によって制限がかかることもあります。

以下のようなケースでは、リースバックの利用が難しい、あるいは断られる可能性があります。
- オーバーローンの場合
- 保証会社の審査に通らないケース
- 共同名義人の同意が得られないケース
- 物件に瑕疵や重大な問題がある場合
- エリアや物件種別が対象外となる場合
これらはリースバックの利用が難しいケースの一部ですが、事前に条件を確認しておくことが重要です。
次に、それぞれのケースについて詳しくご説明します。
オーバーローンの場合
リースバックを希望しても、住宅ローンの残債が物件の売却価格を上回る「オーバーローン」の場合、リースバック契約が成立しないケースがあります。
リースバックでは、売却代金によって住宅ローンを完済し、物件の所有権を移転する必要があります。オーバーローンの状態では残債が残るため、抵当権の抹消ができず、リースバックの手続きが進められません。
対応策としては、金融機関と交渉し、「任意売却」や「債務一部免除」の交渉を行うと良いでしょう。リースバックを検討する際は、ローン残高とリースバック業者の査定価格を早めに把握し、現実的な返済計画と契約形態を検討することが重要です。
保証会社の審査に通らないケース
リースバックでは、売却後に定期借家契約を締結し、住み続けるために賃貸契約を交わします。その際、多くのリースバック業者が保証会社による審査を必要としますが、この審査に通らない場合は定期借家契約を締結できず、リースバック自体が実現しません。
この審査では、収入の安定性や信用情報、過去の家賃滞納歴などがチェックされます。特に、年金生活者や無職の方、信用情報に問題がある方は不利になる傾向があります。対策としては、連帯保証人を立てる、収入証明書を事前に準備するなどが有効です。
リースバックを利用するには、保証会社の審査に通過し、定期借家契約が成立することが最低条件となる点を押さえておきましょう。例えば、家賃の支払いに不安がある方や、過去にクレジットカードの滞納があった方などは、事前に対策を取っておくことで審査に通る可能性が高まります。

共同名義人の同意が得られないケース
リースバックを行うには、物件の売却にあたり共同名義人全員の同意が必要です。
夫婦や親子などの共同名義の場合、たとえ居住者一人でも承諾が得られなければ、リースバックに伴う所有権移転や定期借家契約の締結ができません。このようなケースは、特に相続で複数人が名義人になっている物件で起こりやすく、家族間の意思統一がなされていないと、手続きが進まなくなることもあります。
解決のためには、事前に名義人全員と話し合い、売却の目的やリースバック後の住み方についてしっかり合意を得ることが重要です。定期借家契約の成立にも名義人の同意が必要となるため、スムーズな手続きを進めるには関係者との信頼関係と合意形成が鍵となります。
物件に瑕疵や重大な問題がある場合
物件に重大な瑕疵や問題があると、リースバックの対象にならないことがあります。
例えば、基礎の劣化、再建築不可などの瑕疵や問題があると、買主となるリースバック業者が物件の購入を避ける傾向があります。こうした瑕疵や問題は、再販売価値の低下や賃貸経営上のリスクにつながるため、定期借家契約による継続利用にも支障が出る可能性があります。
対策として有効なのが、「ホームインスペクション(住宅診断)」です。これは、専門家によって物件の劣化状況や修繕の必要性を調べる調査で、事前に物件の状態を把握して必要な補修を行えば、リースバックが成立しやすくなります。
リースバックを実現し、安心して住み続けるためにも、物件の状態を正確に把握しておくことが重要です。

エリアや物件種別が対象外となる場合
多くのリースバック業者は、賃貸需要が高い都市部や交通アクセスの良い地域にサービスを限定しています。そのため、過疎地域や空き家が多い郊外では、リースバックを利用できないケースがあります。
また、店舗付き住宅やシェアハウス、築年数が極端に古い木造住宅なども、リースバックの対象から外れることがあります。
リースバックを検討する際は、定期借家契約を締結できるかどうかも含めて、エリアや物件種別が対象内かどうかを事前に業者へ確認することが重要です。エリアや物件の条件によっては対応可能な業者もあるため、複数のリースバック業者に相談することをおすすめします。
リースバックなど不動産の扱いでお困りでしたら、あきやの未来にご相談ください
リースバックや不動産に関する不安や疑問は、専門的な知識が求められるため、ひとりで抱え込まずに専門家へ相談することが大切です。特に、契約内容や条件の確認が不十分だと、思わぬトラブルにつながることもあります。

あきやの未来(常総・筑西・坂東・桜川・つくば店)では、地域に密着したきめ細やかな対応を心がけており、リースバックなどの不動産に関するご相談を無料で承っております。古い家やローンが残る物件でも、柔軟な対応が可能です。
また、あきやの未来では、仲介による不動産売却や買取対応、空き家の管理など幅広く対応しています。「リースバックの仕組みを理解しておきたい」「相続した実家をどうしたらいいか選択肢を知りたい」「遠方の空き家の管理に困っている」「住宅ローンの返済に悩んでいる」など、不動産に関するお悩みごとは、ぜひあきやの未来にご相談ください。経験豊富なスタッフが、あなたの不安を解消し、最適なプランをご提案いたします。
まずは無料相談からでもお気軽にご連絡ください。