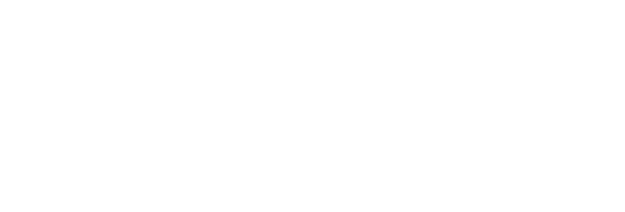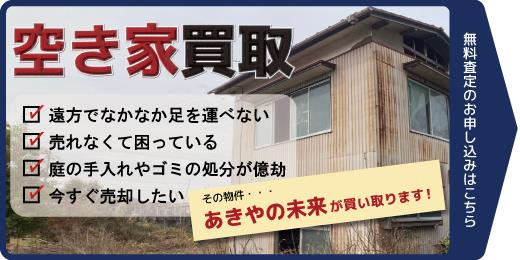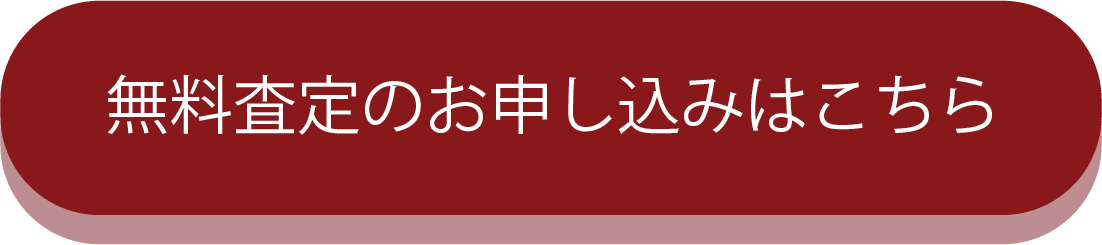リースバックの家賃例をご紹介!仕組みと相場もあわせて解説します
自宅を売却しながらも住み続けたいと考えたことはありませんか。
リースバックとは、住んでいる自宅を売った後も賃貸契約を結ぶことで住み続けられる仕組みです。大きな資金を確保できる一方で、毎月の家賃負担が発生するため、契約内容を理解することが重要です。
家賃は物件の買取価格や市場相場によって決まりますが、具体的な金額を把握していないと、想定以上の支出になりかねません。例えば、都市部のマンションと地方の一戸建てでは、家賃に大きな違いがあります。こうした例を参考にすることで、必要な費用感をつかみやすくなります。
例えば、2,000万円で売却した物件のリースバック家賃が月15万円になるケースもあれば、同じ金額で売却しても地域によっては10万円程度に抑えられる例もあります。また、契約の内容次第では、将来的に買い戻しが可能な例や、一定期間後に契約更新が必要な例など、さまざまなケースが考えられます。
この記事では、リースバックの基本的な仕組みや家賃相場、注意すべきポイントを紹介し、リースバックを検討している方が適切に判断できるようサポートしますので、ぜひご参考ください。
リースバックの基本的な仕組み
自宅を売却しても住み続けたいというニーズに応えるのが、リースバックの仕組みです。

この方法では、所有している不動産を不動産会社や投資家などのリースバック業者に売り、その後に賃貸契約を結ぶことで、引き続き同じ家に住み続けることができます。まとまった資金を確保できるため、住宅ローンの完済や老後資金の確保に活用されることが多いのが特徴です。
リースバックの契約内容は、業者ごとに異なります。例えば、契約期間が定められている場合と、定期借家契約で更新が必要な場合があるため、契約時にしっかり確認することが重要です。
リースバックの契約にはさまざまな例があります。例えば、売却後に買い戻しが可能な例、長期契約が前提となる例、一定期間後に賃料が変更される例など、契約の形態は多岐にわたります。実際に過去のリースバック例を参考にすると、契約内容によって資金計画や住居の安定性が大きく変わることがわかります。
契約前に複数の業者と比較し、適正な条件で契約を結ぶことが大切です。前述の例を踏まえて契約内容をしっかり確認し、ご自身のライフプランに合った選択をしましょう。
リースバック家賃のメリット・デメリットを比較
自宅を売却しても住み続けたいという希望を叶える手段として、リースバックが注目されていますが、契約を結ぶ前にメリットとデメリットをしっかり理解しておくことが重要です。

大きなメリットは、大きな資金を確保しながらも、住み慣れた自宅で生活を続けることができる点です。例えば、住宅ローンの完済や老後資金の確保ができるため、資金繰りの選択肢として有効です。また、売却後も賃貸契約を結ぶため、引っ越しの手間やコストを省くことができます。
一方で、家賃は通常の賃貸住宅よりも高くなる傾向があり、長期的には総支出が増える可能性があります。例えば、都市部の一戸建てと地方のマンションでは家賃の設定に差があるため、契約前に具体的な例を確認しておくことが重要です。さらに、契約期間に制限がある場合、更新ができずに退去を求められるリスクも考慮しなければなりません。
また、リースバックの例として、売却価格と賃料のバランスを重視するケースや、短期間の契約を希望するケースなど、さまざまなパターンがあります。過去の例をもとに自分の状況と照らし合わせ、最適なプランを選ぶことが大切です。
リースバックをご検討の方は、こうした要素を総合的に判断し、ご自身にとって最適な選択肢かどうかを慎重に見極めることが大切です。
リースバック利用時に注意すべきこと
リースバックを活用する際には、契約内容をしっかり確認することが大切です。特に、契約期間や家賃の変動、再売却時の条件を事前に把握しておかないと、将来的に住み続けられなくなるリスクが生じます。

まず、契約期間の確認が重要です。リースバックは「普通借家契約」と「定期借家契約」に分かれています。例えば、定期借家契約の場合、契約期間終了後に再契約できないケースがあり、長期間住み続ける予定がある場合は、契約内容を慎重に検討しましょう。また、普通借家契約の場合でも、途中で契約条件が変更される例があるため、事前に確認が必要です。
次に、家賃の上昇リスクにも注意が必要です。契約当初の家賃が適正でも、再契約時に値上げされる可能性があります。例えば、契約期間が終わる頃に市場相場の変動により家賃が大幅に上がる例もあり、将来的な負担を考慮して契約を結ぶことが大切です。
さらに、信頼できる業者の選定も欠かせません。リースバック業者ごとに買取価格や家賃の設定基準が異なるため、複数の業者から見積もりを取得し、最も条件の良い契約を選ぶことが賢明です。例えば、業者ごとの家賃設定の例を比較し、最も負担が少ない条件を選ぶことで、長期的に安心して住み続けることができます。慎重な比較を行い、将来的なリスクを回避しながら、リースバックを最大限に活用できるようにしましょう。
リースバックの買取価格の相場は?
リースバックを利用すると、いくらで売却できるのか、多くの人が気になるポイントでしょう。

リースバックの買取価格は、物件の市場価値や立地条件、築年数など複数の要因によって決まります。例えば、都市部のマンションの例では、駅近で築年数が浅いと市場価格の7割程度で買取されることがあります。一方、郊外の一戸建ての例では、築年数が古くなると市場価格の6割程度まで下がるケースが一般的です。
買取価格を算出する際には、まず不動産の査定が行われます。この査定では、物件の築年数や間取り、エリアの需要などを評価し、さらにリースバック後の家賃収益も考慮されます。例えば、人気エリアのリースバックの例では、賃貸需要が高いため、買取価格が相場よりも上がることがあります。
また、賃貸需要が高い地域では、買取価格が比較的高くなる傾向があります。一方で、築年数が古い物件や立地が不利な場合、査定額が低くなる可能性があります。
少しでも高く売却するためには、複数のリースバック業者から見積もりを取り、最も条件の良い業者を選ぶことが重要です。また、物件の魅力を高めるために簡単な修繕を行うことも、査定額を上げる有効な手段となります。これらの成功事例の例を参考にしながら、より良い条件でリースバックを進めましょう。
リースバックの家賃は高い?どのように決まるのか解説します
リースバック利用時に最も気になるのは、家賃の決まり方ではないでしょうか。

家賃の設定は、物件の買取価格や賃貸市場の相場、契約条件によって大きく変動します。一般的に、家賃は物件の買取価格に比例し、買取価格の10%程度が年間家賃として設定されることが多いです。例えば、都市部のマンションの例では、賃貸需要が高いため、期待利回りが低くなり、家賃も比較的抑えられる傾向にあります。一方、郊外の一戸建ての例では、賃貸需要が低いため、利回りが高く設定され、家賃が割高になることがあります。
買取価格に対して、期待利回り(年率7%~13%)を掛け算し、それを12カ月で割った後、物件の維持にかかる必要経費を加算することで、その物件の月々の家賃が決まります。
式で表すと、次のようになります。
月々の家賃(賃料)= 買取価格 × 期待利回り(年率) ÷ 12カ月 + 物件の必要経費
例えば、物件の買取価格が1,000万円で、期待利回りが8%の場合、家賃がどれくらいになるかを計算することができます。
- 買取価格1,000万円、期待利回り8%の場合:
月々の家賃 = 1,000万円 × 8% ÷ 12カ月 + 必要経費
また、家賃を決定する際には、エリアの賃貸相場が重要な要素となります。例えば、賃貸需要が高い都市部では家賃が高くなりやすく、逆に地方では比較的安価に設定される傾向があります。
家賃を抑えるために、複数のリースバック業者の見積もりを比較することが有効です。条件をしっかり確認し、交渉を重ねることでより有利な契約を結ぶことが可能になります。過去の契約事例を参考にしながら、最適な選択肢を見つけましょう。
リースバックの賃料の具体例!ケース別に解説
リースバックの家賃は、物件の特性や立地条件、さらには住宅ローンの残債の有無などによっても大きく異なります。
例えば、都市部のマンションの例と地方の一戸建ての例では、家賃の相場に差があります。都市部では賃貸需要が高いため、家賃は市場相場に準じた適正価格になりやすいですが、地方の一戸建てでは、需要が低いため家賃が割高になる傾向があります。
また、住宅ローンの残債がある場合の例では、リースバックの家賃が高めに設定されることがあります。これは、業者が買い取る際にローン残債を考慮し、収益性を確保するためです。たとえば、ローン残債が多く、買取価格が抑えられた場合、賃料設定が割高になるケースが見られます。
このように、リースバックの家賃は、物件の条件や契約内容によって異なる例が多く、実際の契約事例を参考にすることで、適切な価格帯を把握できます。例えば、ある地域では同じ築年数の物件でも、駅からの距離によって家賃が数万円変わる例があります。
ここからは、具体的なリースバック家賃の例をケース別にご説明しますので、ご自身の状況と照らし合わせて参考になさってください。
例1:住宅ローンが残っている場合の家賃例
住宅ローンの残債があるままリースバックを利用すると、買取価格からローン残債を差し引いた金額が手元に残ります。しかし、その後の負担を考慮しなければ、資金計画が崩れる可能性があります。では、具体的にどのような家賃が設定されるのでしょうか。
例えば、市場価格3,000万円の物件が2,400万円で買取された場合、リースバックの家賃は一般的に買取価格の10%程度が年間賃料として設定されます。仮に年利10%で計算すると、年間家賃は約240万円、月額にすると20万円前後になります。
また、同じような物件でも立地や築年数によって家賃設定は異なります。例えば、都市部のマンションでは需要が高いため、リースバック後の家賃が市場相場と同等かそれ以上になるケースが多いですが、地方の一戸建ての場合、家賃の設定が比較的低く抑えられる例もあります。
さらに、リースバック業者によって家賃の計算基準が異なるため、異なる条件の例を比較することが重要です。例えば、一部の業者では家賃を固定せず、定期的に見直しを行う契約もあるため、長期的に住む場合は慎重な検討が必要です。
家賃負担を軽減するためにも、複数のリースバック業者に見積もりを依頼し、過去の家賃設定の例なども提示してもらいながら条件を比較することをおすすめします。

例2:築年数や立地による家賃の違い
リースバックの家賃は、物件の築年数や立地条件などによって大きく変わります。
新築や築浅の住宅は買取価格が高く設定されるため、家賃もその分高額になりがちです。一方、築年数が古い物件や地方の住宅では買取価格が低くなるため、家賃も比較的抑えられる傾向があります。
例えば、東京都心の築5年のマンションでは、買取価格の約10%が年間家賃として設定されることが多く、月額30万円以上になるケースも珍しくありません。
れに対して、同じ築5年でも郊外の住宅では買取価格が都心の物件より低くなるため、家賃が15万円程度に抑えられる例もあります。
また、築年数が20年以上経過した地方の一戸建てでは、買取価格が大きく下がるため、家賃が10万円以下になる場合もあります。例えば、賃貸需要が低い地域では買取価格が下がり、それに応じて家賃も低めに設定される例が多く見られます。
リースバックを検討する際には、実際の市場相場や過去の契約の例を業者に確認することが重要です。リースバック業者ごとに家賃の計算方法が異なるため、過去の事例を参考にしながら、慎重に条件を比較しましょう。
例3:高齢者向けリースバックの家賃事例
老後も住み慣れた家で安心して暮らしたいと考える高齢者にとって、リースバックは選択肢の一つになります。

ただし、高齢者向けのリースバックでは、通常の賃貸契約とは異なり、家賃のほかに管理費や生活支援サービス料が加算される可能性があります。そのため、総支出を事前に把握し、無理のない契約を結ぶことが重要です。
例えば、東京都内の築10年のマンションでは、通常のリースバック家賃が月額20万円前後になる例があります。しかし、高齢者向けリースバックでは、家賃に加えて管理費や生活支援サービス料が月5万円程度加算され、結果的に総額25万円以上になる例も少なくありません。
一方で、地方の一戸建てでは、買取価格が低めに設定されるため、リースバックの家賃も比較的安くなり、月額10万円以下で契約できる例もあります。これにより、都心と地方の違いを把握し、自身のライフプランに合った選択をすることが大切です。
高齢者向けリースバックを検討する際は、過去の契約の例を参考にしながら、家賃と付帯サービスの費用を総合的に考え、長期的に負担が増えないか確認することが重要です。リースバック業者によって条件が異なるため、複数の業者に相談し、最適な契約内容を選びましょう。
リースバックの利用をご検討の方は「あきやの未来」にお任せください
リースバックの利用をご検討されている方は、あきやの未来(常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店)にご相談ください。

リースバックを活用したいと考えていても、「家賃の相場は適正なのか」「契約内容に不安がある」といった疑問を抱えている方は多いでしょう。例えば、同じ地域でも業者ごとに家賃設定が異なりますので、適正価格がわかりにくいことがあります。納得のいく条件で契約を進めるためには、リースバックに詳しい専門家に相談することが大切です。専門家はさまざまな事例を扱っていますので、ご自身に適したアドバイスを行ってくれます。
あきやの未来は、豊富な実績を持つ不動産会社として、お客様一人ひとりに最適なプランをご提案します。些細なことでも、どうぞお気軽にお問い合わせください。