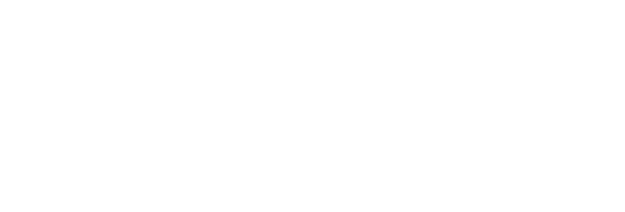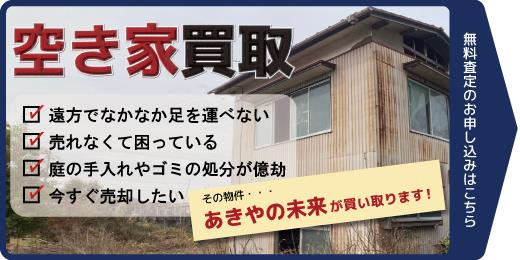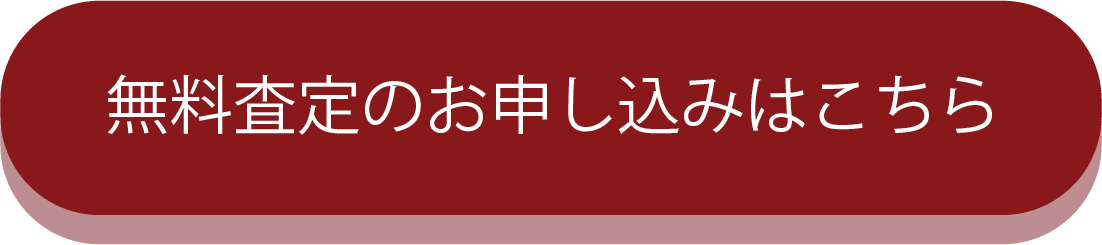リースバックはなぜ相続対策になるのか?相続税との関係や売却によるメリット・デメリットを解説
リースバックが相続対策に活用できるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
リースバックとは、所有する家を売却し、そのまま賃貸契約を結んで同じ家に住み続ける仕組みです。不動産を現金化できるこの方法は、老後資金の確保に加え、相続対策としても注目されています。リースバックを利用すれば、不動産を遺産として相続させるのではなく、生前に現金化することで相続人への分配が容易になり、トラブルの予防につながります。
また、相続対策の一環として、評価額の高い不動産をあらかじめ手放すことで、相続税の負担を軽減できる点も魅力です。リースバックなら生活環境を維持しながらも、将来の相続問題に備える準備ができます。
このように、資産管理と相続対策を両立できる手段として、リースバックが選ばれています。
しかしながら、リースバックにはデメリットもあります。相続は家族に大きな影響を及ぼすため、制度の両面をしっかり理解したうえで検討することが大切です。
まずは、リースバックを相続対策に活用する場合のメリットとデメリットを一覧で確認してみましょう。
【相続対策としてのリースバックのメリット・デメリット】
| メリット |
|
| デメリット |
|
リースバックを相続対策として活用するメリット
リースバックを相続対策に活用する大きなメリットは、不動産を現金化しながら自宅に住み続けられる点です。
不動産は相続時に分割が難しく、共有名義や活用方法をめぐって争いが起こることも少なくありません。しかし、現金化しておけば分配が容易になり、トラブル回避に役立ちます。
また、売却時に「3,000万円特別控除」を利用できる場合があり、税金負担を軽減できるのも魅力です。
さらに、リースバックによる相続対策では、生前に財産整理などの対策を進められるため、相続手続きがスムーズになり、家族の負担を和らげる効果も期待できます。
加えて、不動産の所有権を手放すことで維持費や修繕といった管理の手間を省き、空き家リスクにも備えられます。
このように、リースバックを相続対策として取り入れることで、安心して住み続けながら計画的に資産を整理できる点が大きな強みです。
空き家リスクについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
空き家を放置するリスクについて
リースバックを相続対策として活用するデメリット
リースバックを相続対策に取り入れる場合、いくつかの注意点があります。
まず、売却後は毎月の家賃を支払い続ける必要があり、長期的に経済的負担となる可能性があります。また、買取価格は市場相場より低く設定されることが多く、資産を最大限に活かせない場合もあります。さらに、契約形態によっては、希望する期間ずっと住み続けられない場合があり、将来的に退去を求められるリスクもあります。
加えて、所有権を手放すことで、リフォームや再売却などの自由度が制限される点も考慮が必要です。さらに、相続人間で合意が十分でない場合、資産分配や契約条件をめぐるトラブルに発展することもあります。
このように、リースバック 相続対策には資産整理や税務上の利点がある一方で、生活や契約上の制約が伴うため、事前に十分な検討と家族間の合意が大切です。

リースバックした家に何年住める?契約期間や更新のポイント
リースバックを利用する場合、その家に何年住み続けられるのか、相続対策を検討するうえで非常に重要なポイントです。
一般的に、リースバックは2種類の契約形態があります。
- 普通借家契約
契約期間の決定権は借主にあるため、自動更新が期待できる。リースバックで長く住みたい場合は、普通借家契約を扱っているリースバック業者を選ぶのがおすすめ。
- 定期借家契約
契約期間を2~3年に設定するケースが多い。更新が保証されないため、契約終了後に退去が必要になる可能性がある。
相続対策としてのリースバックは、生活の安定と資産整理を両立するために慎重に計画すべきです。安心して住み続けられるよう、事前に契約期間や更新条件を明確にしておきましょう。
契約者が死亡したらどうなるのか?
リースバックを相続対策として活用する場合、契約者の死亡後の取り扱いについて理解しておくことも大切です。
普通借家契約でも定期借家契約でも、契約期間中であれば相続人は原則として従来の条件で住み続けることが可能です。この継続性は大きな安心材料になります。
ただし、賃貸借契約も相続財産の一部とみなされます。賃貸を継続するか、それとも解約するかを決定するためには、遺産分割協議で判断される点に留意が必要です。
リースバックを相続対策に活用する場合は、相続後の生活に大きな影響を与える可能性があるため、家族と話し合っておくことが大切です。
契約者が死亡した場合、リースバック契約や家の所有権はどうなる?
リースバックでは、売却と同時に所有権が買主(リースバック業者)に移ります。これは相続対策の観点から見ると、その相続対象から外れるため、相続税の課税額を抑えることが可能ということです。
ただし、所有権が変更されるので、家に対する自由度や権利が制限されることも忘れてはなりません。住み続けるためには、買主との契約条件を守る必要があります。
相続対策としてリースバックを活用する場合、資産整理だけでなく、今後の生活設計にも大きく関わります。相続対策におけるリースバックの主な目的は、資産の現金化と分割のしやすさです。自宅を資産として残すか、現金化して分けやすくするかは、家族構成や相続人の意向によっても変わります。リースバックを活用する際は、その選択がもたらす長期的な影響も理解しておくことが大切です。

相続対策にリースバックを活用する場合のリスクと注意点
リースバックは、不動産を現金化しながら住み続けられる仕組みのため、相続対策として有効な選択肢の一つです。
しかし、以下のように、事前に把握しておくべきリスクもあります。
- 売却価格が市場価格より低くなる可能性がある
- 家賃の支払いが継続する
- 相続税の軽減効果が限定的な場合もある
ここでは、リースバックを相続対策として検討する際に注意すべきポイントを、3つの視点から解説します。

1. 売却価格が市場価格より低くなる可能性がある
リースバックでは、自宅を買主であるリースバック業者に売却したうえで賃貸として住み続けますが、この売却価格は一般の市場価格よりも低く設定されるのが一般的です。これは、買主が再販売リスクや賃貸管理の負担を見越して価格を抑えるためです。
その結果、相続財産としての不動産の評価額が減少し、相続税対策としては一部有効ですが、想定していた資産価値が得られないリスクが生じることもあります。
そのため、事前に複数の業者に査定を依頼し、適正な価格で売却できるかを確認することが大切です。
2. 家賃の支払いが継続する
リースバック後は売却した家に住み続けることが可能ですが、居住するには家賃を支払う必要があります。契約形態や地域によっては、家賃が相場より高額になるケースもあるため、長期的な生活資金とのバランスを見極めることが大切です。
特に、高齢者や年金生活者の場合、売却益を一括で使ってしまうと、その後の家賃支払いが困難になる恐れがあります。
家賃の支払いが生活資金に及ぼす影響や、契約更新時の家賃変動にも注意が必要です。
契約更新の条件や家賃上昇の有無なども含めて、契約内容を慎重に確認し、将来的なコスト増に備えた資金計画を立てましょう。
3. 相続税の軽減効果が限定的な場合もある
不動産を現金化することで、一時的に相続税の納税資金を確保できるのはリースバックの利点ですが、すべてのケースで効果があるわけではありません。
現金化した資産も相続財産に含まれるため、総資産の評価額が基礎控除額を超えると相続税が課される場合があります。
また、リースバックを活用したとしても、小規模宅地等の特例など、本来不動産に適用できた節税措置が利用できなくなる可能性もあるため注意が必要です。リースバックだけでは不十分なケースもありますので、他の相続対策と組み合わせて計画的に行うことが重要です。
自分の資産状況に合った相続対策を考えるために、税理士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。
なお、リースバックを相続対策として利用する際、契約や相続人との調整などで思わぬトラブルが起きることもあります。特に、高齢や認知症の症状がある場合は、一人で判断や手続きを行うのが難しくなることがあります。その場合は、成年後見制度を活用することで、法的に保護された手続きのもと、自宅の売却や資金管理を安全に進めることが可能です。
詳しくは、以下の記事で解説していますので、参考になさってください。
成年後見制度を活用した売却方法はこちら

リースバックなどの相続対策でお困りの方は、あきやの未来にご相談ください
「相続対策としてリースバックを活用できるのか知りたい」「他の方法と比較して最適な選択肢を見つけたい」とお考えではありませんか?
今回の記事では、リースバックを相続対策として活用する際のメリットや注意点をご紹介しましたが、実際にはご家庭の状況によって最適な選択肢は異なります。
あきやの未来(常総・筑西・坂東・桜川・つくば店)では、相続や不動産に関する豊富な知識と経験を持つスタッフが、リースバックをはじめとするさまざまな対策をわかりやすくご提案しています。売却や買取、空き家管理まで幅広く対応しておりますので、どうぞ安心してご相談ください。
ご自身やご家族にとって納得のいく相続対策を進めるためにも、まずはお気軽にお問い合わせください。