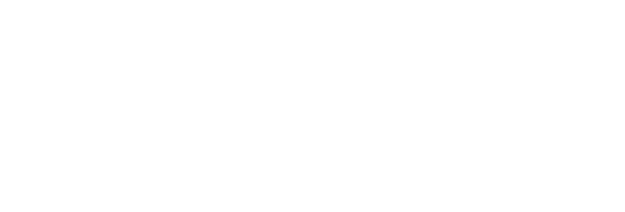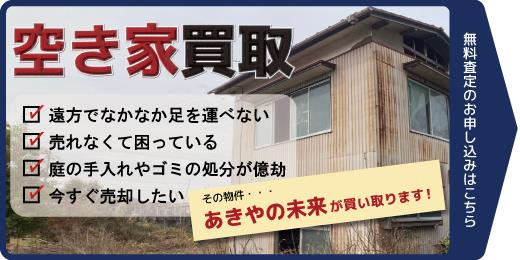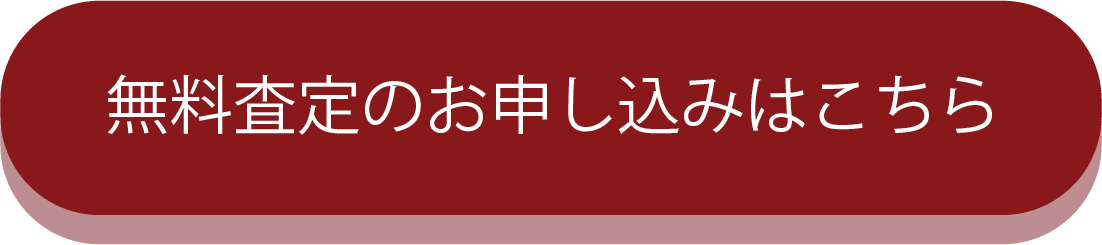リースバックの売却価格は安いって本当?相場と決まり方を解説
リースバックの売却価格はどのように決まるのか、気になっている方もいらっしゃるかと思います。
リースバックの売却価格は、一般的な不動産売却と比べると市場価格より低くなることが多いですが、これはリースバック業者が一定のリスクを追うことに起因しています。
リースバックでは、物件を買取った事業者が売主にそのまま賃貸するため、将来の物件価値の下落や賃料未払い、再販売時のリスクなどを想定しなければなりません。これらのリスクを加味した結果、売却価格が抑えられるのです。
通常の不動産売却では、引き渡しが完了すれば売主と買主の関係は終了します。しかし、リースバックの場合は、契約後も賃貸契約を通じて関係が続くため、より慎重な売却価格の設定が必要です。
それでも、住み慣れた自宅にそのまま住み続けながら資金を調達できるという大きなメリットから、多少売却価格が抑えられてもリースバックを検討する人は少なくありません。
売却価格は市場価格の60~80%が目安
リースバックにおける売却価格の相場は、市場価格の60~80%が一般的な目安とされています。

例えば、通常の不動産売却で3,000万円の査定がつく物件でも、リースバックを利用する場合は1,800万円~2,400万円程度の売却価格になるケースが多く見られます。このような価格差が生じるのは、リースバック業者が物件購入後に賃料収入を得る一方で、将来的な再販リスクも背負っているためです。
リースバック業者は物件を買取った後、賃料収入を得ながら将来的な物件の再販も視野に入れており、「投資利回り」を重視しています。一般的に、年間の家賃収入が物件購入価格の5~8%程度になるように逆算して売却価格を決定します。高い利回りを確保するために、買取価格(=売主の売却価格)を抑える必要があるのです。
さらに、リースバック後に借主が退去した後の空室リスクや、将来の不動産価値下落リスクなども考慮し、売却査定価格に反映されます。特に、築年数が経過した物件や、地方の需要が低い地域では、こうしたリスクを加味して物件の売却価格がさらに低く設定されることもあるでしょう。
査定価格に影響する主なポイント
リースバックで提示される売却価格は、さまざまな査定要素によって決まります。

まず重要なのは「立地」です。駅や商業施設へのアクセスが良く、生活利便性の高いエリアは将来的な再販の見込みがあるため、売却価格が高く評価されやすい傾向にあります。
次に「築年数」と「物件の状態」も大きな要因です。築浅で修繕の必要が少ない物件ほど、リースバック業者にとって再販しやすいため、売却価格が高くなります。
また、「周辺の不動産相場」や「賃貸需要」も査定に大きく影響します。需要の高い地域では、リースバック後の安定した賃料収入が見込めるため、業者はリスクを抑えて比較的高い売却価格を提示できます。加えて、「法的制限」や「土地利用の可能性」などもチェックされ、開発の自由度が低い地域では売却価格が下がることもあります。
これらの項目が総合的に評価され、リースバックにおける最終的な売却価格が決定されるのです。
売却価格だけで決めてない?家賃の相場と損しないための関係性とは
リースバックを検討する場合、つい売却価格の高さばかりに目が行きがちですが、それだけで契約を決めてしまうのは危険です。
というのも、リースバックでは売却価格と家賃が密接に連動しているため、売却価格が高い場合、その分だけ毎月の家賃も高くなる傾向があるからです。この関係性を理解することが、リースバック利用で損をしないための重要なポイントとなります。
例えば、売却価格が2,000万円と高額であっても、その対価として設定される家賃が月額10万円を超えるケースもあります。一方で、売却価格が1,800万円と低めでも、月額家賃が6万円程度に抑えられることがあります。
このように、「売却価格が高い=お得」とは限らず、長期的に住み続ける予定であれば、家賃負担の方が総費用に大きく影響する可能性があります。
理想的なのは、適正な市場価格に近い売却価格設定と、周辺相場に沿った適正な家賃のバランスが取れた提案を受けることです。そのためには、複数のリースバック業者に査定を依頼し、売却価格と月々の賃料のバランスを丁寧に精査することをおすすめします。

家賃は「買取価格×利回り÷12ヶ月」で決まる
リースバックにおける家賃は、基本的に以下の方法で算出されます。
家賃=買取価格×年間利回り÷12ヶ月
ここでの「利回り」とは、リースバック業者が不動産投資に対して期待する年間収益率を意味します。一般的なリースバック業者の利回りは、年5~8%程度が相場です。
具体例で見てみましょう。例えば、物件の売却価格が2,000万円で、業者が年間利回り6%を想定している場合、年間の家賃収入は2,000万円×6%=120万円となります。これを12ヶ月で割ると、月額家賃は10万円という計算になります。同じ物件で、年間利回りを7%と設定する場合は、月額約11.7万円、5%の利回りなら月額約8.3万円というように変動します。
このように、物件の売却価格が同じであっても、設定される利回りによって家賃が大きく変わります。また、地域や物件の特性によって適正な利回りは異なるため、周辺の賃貸相場と比較し、明らかに割高な家賃設定になっていないかをチェックすることが大切です。リースバック契約では売却価格と家賃のバランスが重要なポイントになります。
家賃が高くなるケースとその対策とは?
リースバックで家賃が高くなるケースには、いくつかのパターンがあります。

- 物件の売却価格が周辺相場より高すぎる
高い売却価格は一見メリットに見えますが、前述のとおり、売却価格が高いとそのまま家賃に跳ね返ってきます。
- リースバック業者が設定する利回りが高すぎる
投資リスクが高いと判断された物件では、リースバック事業者が高い利回りを設定することがあります。
- 契約条件が不利な場合
短期間の賃貸契約や、更新時の家賃値上げ条項があると、将来的に家賃負担が増加する可能性があります。
これらの対策として、複数のリースバック業者に査定を依頼し、売却価格と家賃のバランスを比較検討することが重要です。
また、賃貸契約は長期固定が望ましく、家賃改定条件や更新料についても事前に確認・交渉すべきです。さらに、リースバック後の家賃が周辺相場と比べて適正かどうかを第三者に確認してもらうことも有効です。査定価格や家賃設定に交渉の余地があるケースもあるため、業者と納得いくまで話し合いましょう。
リースバックの仕組みと利用の流れを解説
リースバックとは、自宅などの不動産を売却した後も、そのまま住み続けられる仕組みです。ここでは、リースバックの基本的な取引の流れについてご説明します。

リースバックの取引は、まず複数のリースバック業者に査定を依頼するところから始まります。各リースバック業者から提示された売却価格や家賃、契約期間などの条件を比較検討し、最も自分に合った業者を選びます。売却価格が高くても家賃負担が重ければ本末転倒ですので、バランスを見極めることが重要です。
また、リースバック業者とは不動産の売買契約とあわせて賃貸契約も結び、物件の引き渡し(所有権の移転)後は「賃借人」としてそのまま住み続けることになります。一般的には、査定から契約締結まで2~4週間程度、契約から売買代金受け取りまでさらに2~3週間ほどかかります。売却価格を早く現金化したい方には、スピード対応可能なリースバック業者もあります。
注意すべきは、不動産売却後は「所有者」から「借主」へと立場が変わる点です。固定資産税の負担がなくなる一方、家賃の支払いが始まります。売却価格だけでなく、契約内容全体をしっかり確認しながら進めることが大切です。
リースバックはどんな人に向いているの?
リースバックは、「まとまった資金が必要だが住み続けたい人」に最適な選択肢です。

例えば、住宅ローンの返済が困難になった高齢者は、リースバックによって物件の売却価格を利用してローンを一括返済しつつ、慣れ親しんだ住まいにそのまま居住できます。
また、相続税や事業資金、教育資金などの急な出費に備えたい方も、リースバックによって資金を確保しながら生活の安定を保てます。金融機関の融資が難しい場合でも、売却価格を活用した柔軟な資金調達が可能です。
将来的に住み替えを予定しているが、今すぐには引っ越したくない方にも向いています。例えば、老後は子どもの近くに引っ越す予定だが、まだ数年は住み慣れた家に居住したい場合、生活設計にゆとりが生まれます。
リースバックのメリット・デメリットと注意点を解説
リースバックには「住み続けながら資金を得られる」という魅力がありますが、売却価格や家賃、契約内容によってそのメリットが十分に活かせるかどうかは変わってきます。
リースバックは昨今注目されている仕組みですが、リースバックによるトラブルが増えているのも事実です。
トラブルの要因としては、リースバック利用者がその仕組みを十分に理解しないまま契約を結んでしまうことや、リースバックを利用した悪徳業者が存在していることなどが挙げられます。そのため、リースバックを検討している方は、仕組みやメリット・デメリット、注意点について十分理解し、リースバック業者の提案が自分に合っているかをしっかり判断することが大切です。
ここからは、リースバックの主なメリットや、注意すべきデメリットやリスクを具体的に解説します。そして、損をしないための「売却価格と家賃のバランス」の考え方についてご紹介しますので、参考になさってください。
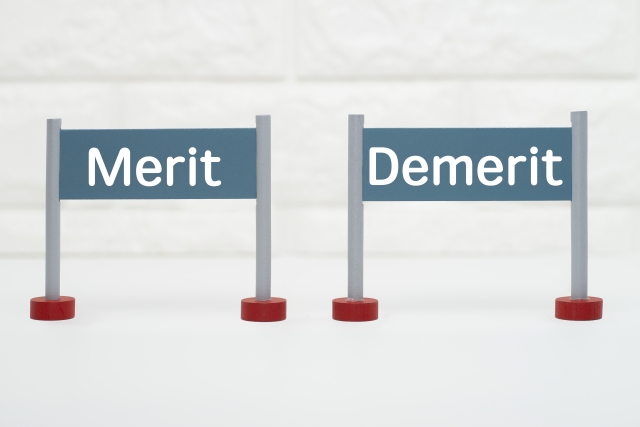
リースバックのメリット
リースバックの最大のメリットは、自宅を売却した後も引き続き住み続けられることです。売却価格を現金化しながら、生活環境を変えずに済む点が大きな利点といえます。売却価格を短期間で調達できるため、急な資金需要にも対応可能です。
また、契約内容によっては将来的に買い戻せる可能性があり、生活再建や資産回復を視野に入れた柔軟な対応ができます。そして、物件の売却によって所有権が移るため、固定資産税や建物修繕といった維持費が不要になる点も経済的負担の軽減につながります。
リースバックは、条件が合致する方にとって、住環境を維持したまま資金ニーズに応える手段として、有効な選択肢といえるでしょう。
リースバックのデメリット
リースバックには注意すべきデメリットもあります。
まず、前述のとおり、売却価格は市場価格より低くなる傾向があり、60~80%程度になることが一般的である点です。
また、賃貸契約には期限があるため、再契約できない場合は退去を求められるリスクもあります。さらに、高めに設定された家賃により、長期間住み続けるとトータルコストがかえって割高になるケースもあります。
加えて、住宅ローンが多く残っている物件では、売却価格より残債の方が高い場合、リースバック自体が成立しないこともあるため注意が必要です。
これらのデメリットを正しく理解し、事前に条件をよく確認することが大切です。
以下の記事でも、リースバックのデメリットについて詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
家のリースバックでデメリットを回避する方法!後悔しないためのポイントを解説
最終判断の前に!売却価格と家賃のバランスを見直しましょう
前述のとおり、リースバック契約では「売却価格が高くなれば、それに比例して家賃も高くなる可能性がある」という仕組みをしっかりと認識しておくことが大切です。
リースバックでは「売却価格が高ければ得をする」とは一概に言えません。なぜなら、売却価格が高くなるほど家賃も上がる傾向があるため、長期的に見ると家賃負担が重くなってしまう可能性があるからです。最終的な支出総額を考慮すると、単に売却価格が高い提案よりも、家賃とのバランスが取れた提案の方が、結果的に経済的なメリットが大きくなる場合もあります。
リースバックで失敗しないためには、売却価格と家賃を個別に見るのではなく、総合的なコストとして捉え直すことが重要です。複数のリースバック業者の見積もりを比較し、ライフプランに合った最適な選択をしましょう。
また、リースバックで新たに発生する費用や、固定資産税を誰が負担するのかも、しっかり把握しておくことが大切です。
詳しくは、以下の記事で詳しく解説しています。
リースバックで新たに発生する費用や固定資産税の扱いについてはこちら
まとめ:売却価格と家賃のバランスがカギ!後悔しないための第一歩を
リースバックを利用して自宅の売却を検討している方は、あきやの未来(常総・筑西・坂東・桜川・つくば店)にご相談ください。

この記事では、リースバックの売却価格の相場や家賃との関係性、また、リースバックの仕組みやメリット・デメリットなどについて解説しました。繰り返しになりますが、リースバックにおいて、売却価格と家賃のバランスを考えることが、とても重要になります。リースバック業者からの提案を安易に受け入れず、複数の業者に見積もりを取り、十分な比較検討を行いましょう。
あきやの未来は、茨城県西エリアに特化した不動産会社です。不動産の仲介売却から、不動産の買取り、空き家の管理まで、お客様のご希望に添えるよう幅広く対応しています。リースバックをご検討中の方でも、他の選択肢の方が最適なケースもあるでしょう。豊富な知識と経験を持つスタッフが、お客様のご希望にあわせてしっかりご提案いたします。
些細なことでも構いません。どうぞお気軽にお問い合わせください。