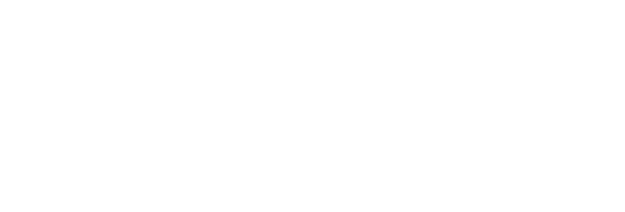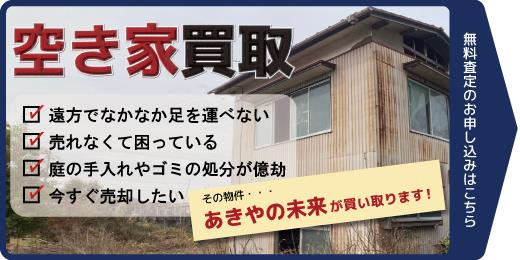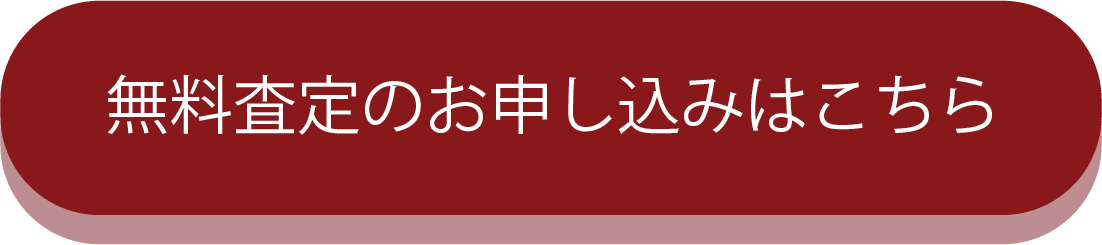家売却の減価償却とは?知っておきたい基礎知識
*減価償却
土地以外の家などの建物や備品、また車両などの固定資産の価値を減らしていくことで計上される費用のことを減価償却費と呼びます。
家などの建物や備品、車などの固定資産は使用していくにつれて価値が下がります。減価償却という考えは会計特有の決まり事で減少分を計算したものになります。
土地の価格は市況によって変動しますよね。しかし、会計上は土地の価値は時間が経っても変わらないものとされています。
不動産においては土地価格と建物価格と分けて考えます。その上で建物価格に限定し減価償却を計算していきます。
*定額法と定率法
減価償却には定額法と定率法があります。
定額法に関して見ていきましょう。これは固定資産の耐用年数において、毎期均等額の減価償却費を計上するという方法になります。
建物購入代金×0.9×経過年数×償却率という数式で減価償却を計算しましょう。
定率法は固定資産の取得費から減価償却累計額を差し引いた未償却残高に対して毎期一定の償却率を上乗せして減価償却費を計上していきます。
定率法を用いると定額法より資産の価値が早いスピードで減っていくでしょう。
アパートや賃貸マンションという貸付用の物件、また事業用の物件を事業用不動産と括ります。建物購入金額に90パーセントを掛け合わせ、償却費と業務に使われた月数を12で割ったものになります。事業用不動産において、取得する際の費用は年初未償却残高がベースとなります。
家などの居住用の建物を指す非事業用不動産においては、減価償却は上記の建物購入金額に90パーセントを掛け償却費と経過年数も掛けて計算しましょう。
不動産所得の必要経費の中で、減価償却費は高い割合を占めるため、減価償却費によって不動産所得が変わってきます。
償却資産を細かく分類することで、減価償却費を増やすことができます。建物の工事に関して、キッチン、ユニットバス、トイレといった設備が含まれています。これらを建物本体部分と設備部分とで分けて考えると償却費を多く計上することができるでしょう。
不動産に関しての減価償却の計算方式のトレンドというものがあります。平成28年の法改正以降は新築の不動産に関しては定額法しか認められなくなりました。一方、法改正以前に登記完了済の不動産物件においては、定額法と定率法を両方使えます。
不動産物件以外を対象とする領域では定率法が主流のものもあります。家の売却で一般的な知識会計を行うという観点では、定額法と定率法の両方について知識を持ち理解しておくことが大事だといえるでしょう。
家売却時に減価償却を考慮すべき理由
課税譲渡所得を計算する場合に、減価償却を計算する必要があります。
これは家などの不動産の売却代金から課税対象の譲渡所得を計算する場合に、不動産の購入代金を必要経費として計上する必要があるからでしょう。
建物を手に入れて20年間が経つと、新築ではなく築20年という状態になってしまいます。建物の取得費は購入代金または建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となっています。
不動産売却を目的とし、確定申告で税金を計算するためには減価償却計算を行う必要があります。売却する不動産に建物が含まれている場合には必ず耐用年数を調べましょう。
耐用年数は建物の用途と構造によって変わってくるので注意することが必要です。
減価償却を活用した節税のポイントと計算方法
減価償却を正しく計算した上で家の売却時の節税に繋げていきたいですよね。そのためには家の耐用年数や償却率を加味した上で、減価償却費の算出を行いましょう。家の耐用年数によって減価償却費は大きく左右されていきます。
家の築年数が法的な築年数を超えているかどうか確認しましょう。これは節税効果にも影響が出ます。
家の築年数が耐用年数を上回っている場合、減価償却費は中古資産の経過期間×0.2という式によって導き出されます。
経過年数が耐用年数より短い場合、新品物件の場合の耐用年数−中古資産における経過期間+中古資産における経過期間に0.2を掛けたものというような計算式になります。
節税という観点では、築年数が長くて耐用年数が短い不動産物件を優先的に購入するということが必要になるでしょう。家の耐用年数が短くなるほど、年間当たりの減価償却費は高くなります。
その分、課税対象の事業所得を少なくすることができます。
償却率を考えることも大切です。償却率は国税局が物件の状態によって定める数値になります。定期的に改定されるので、都度確認することが必要になります。不動産物件を売却する前に事前に確認しておきましょう。
不動産売却時には減価償却の計算が重要
今回は家の売却時における減価償却または計算を行う上で観点となるものをお伝えしました。
家などの不動産の売却時には減価償却を考慮することが重要です。
減価償却は、建物や備品、車両などの固定資産の価値が減少する分を費用として計上する方法です。定額法と定率法の2種類の計算方法があり、節税に活用できます。
減価償却費は不動産所得に大きな影響を与えるため、家などの物件の耐用年数や築年数を把握し、適切に計算することが必要です。さらに、家の売却時には譲渡所得計算において減価償却費を差し引く必要があり、正しい計算が節税に繋るでしょう。
参考になれば幸いです。